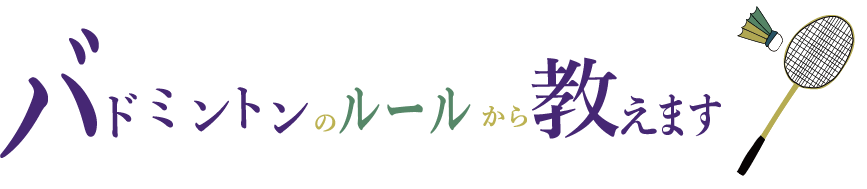バドミントンで空振りしてしまうのはなぜでしょうか?しっかりとシャトルを見てラケットを振っているはずなのに空振りをしてしまうのは初心者のときによくある話です。
バドミントンで空振りしてしまうのはなぜでしょうか?しっかりとシャトルを見てラケットを振っているはずなのに空振りをしてしまうのは初心者のときによくある話です。
当然、プロでも初心者の時が必ずあって空振りを経験しています。空振りは誰しもが通る道ですので、恥ずかしがる必要はまったくありません。
このページでは空振りを減らす方法について解説しています。
バドミントンで空振りするのはなぜか?

空振りをしてしまう理由と対策について順番に解説していきます。
視力の問題
そもそもの問題として目でしっかりとシャトルを捉えられていますか?何か原因があってシャトルを見えづらく感じている、もしくは見えていないかもしれません。ここでは2つの可能性を提示します。
1つめは静止視力に問題があるケースです。静止視力は目と見る対象物が動いていない状態で物体を見る力です。近視になると近くのモノは見えるが、遠くのものがぼやけて見えにくくなります。また乱視になると遠近にかかわらずモノが二重に見えたりブレたりします。
当然ですが、目がしっかりと見えていないとシャトルは見えません。普段はコンタクトレンズやメガネに頼らなくても、日常生活に支障はなくともバドミントンをするための視力はない恐れがあります。
他のスポーツ、とりわけ球技の中においてバドミントンの球であるシャトルは小さいです。特に天井付近へ高く打ちあがったシャトルを見失ってしまっても視力が弱ければ仕方ないでしょう。
この視力の問題に関してだけは練習方法だけでは解決できませんので、コンタクトレンズやメガネなどで矯正してください。
特に視力に問題がないのにもかかわらず空振りをしてしまう場合は、動体視力が原因かもしれません。これが2つめの可能性です。動体視力とは動く物体を見る視力のことです。![]() したがって「私は目が悪い=視力が弱いから見えない。」ではありません。
したがって「私は目が悪い=視力が弱いから見えない。」ではありません。
もし動体視力が低くてもバドミントンの上達を諦める必要はありません。なぜなら動体視力は目の筋力を鍛えれば向上するからです。ぜひ下記のページで紹介されている動体視力トレーニングをしてみてください。
参考:動体視力は今から鍛えられます!/キューサイ【公式】通販サイト
シャトルを見ていない
当然ですが、シャトルを見ていないとラケットにシャトルは当たりません。もっと言えば、シャトルがラケットのガット(ストリングス)面に当たるその瞬間までをしっかりと見ていないといけないのです。
ラケットを大振りして前傾姿勢になってしまい、最後までシャトルを見ていない可能性があります。この場合は無駄にラケットを振り回さず、コンパクトなフォームで打てるようになればシャトルを見る余裕が生まれるので空振りを減らせるはずです。
これはオーバーヘッドストローク(頭上付近でラケットを振ること)だけに限らず、全てのストロークに共通して言えます。また打点が自身の体より後ろになっていると空振りの原因になります。
人間の上下視野は上方向がおよそ60度。下方向が約70度です。つまり自分の体より後ろで打つとシャトルをしっかりと目で追えていないはずです。そのような状態では空振りしてしまうのも仕方ありません。シャトルを自分の体より前で捉えられれば、目でも追えるようになるはずです。
参照元:中心視野と周辺視野|Hondaの安全運転情報誌 Think Safety
バドミントンのショットは、ほぼすべて自分の体より前で打ちます。ある程度バドミントンに慣れてきて、たまに空振りをしてしまう人はこの基本に立ち返ってみてください。空振りをしてしまって悩んでいるなら、インパクトの瞬間までシャトルを目で追えているか確認してみましょう。
シャトルとの距離感が掴めていない
自分とシャトルとの距離感が掴めていないと空振りをしてしまいます。バドミントンはラケット競技なので、自分の手と実際のシャトルが当たるところが50センチほど離れています。
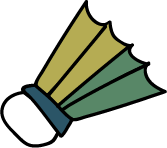
ラケットと腕の長さを合わせた距離感を掴むのにおすすめの練習はシャトル拾いです。練習のやりかたは床に置いてあるシャトルをラケットを使って拾い上げるだけです。繰り返し練習をして10回やったら10回必ず拾い上げられるまで繰り返し練習をしましょう。
また上から落ちてくるシャトルとの距離感覚を養う練習におすすめなのはリフティング(ドリブル)練習です。
リフティング練習はシャトルを真上に繰り返し打ち上げる練習です。フォアハンド(イースタングリップ)・バックハンドどちらでもできるようになりましょう。最初はなるべく高く打ちあげることを目標として、慣れてきたら自分の思い通りの高さで打てるようになるまで繰り返しやってみてください。
またこの練習ではシャトルとの距離感を養えますが、グリップの持ち替えの練習にもなります。腕の力だけでラケットを振るのではなく、手首を使うこととグリップを握りこむことで発生する伝導力で打つ練習にもなります。
参考:バトミントンのラケットの正しい持ち方(握り方)と種類を解説!
力みすぎている
初心者は空振りを恐れて力みすぎている可能性があります。体に力が入りすぎているため全身の筋肉が緊張してしまっているのです。これではいいショットは打てません。
体に必要以上の力が入ってしまうと正しいフォームで打てず空振りをしたり、空振りしなくともいいショットは打てません。遠くに飛ばしたい、力強い下向きのショットが打ちたいと思うあまりに力んでしまうのは仕方ないです。
この力みすぎの問題を解消するには、まず正しいフォームを習得するために素振り練習を推奨します。なぜならシャトルが飛んできたときにどう打てばいいか分からないから、緊張してしまい余計な力が入っている可能性があるからです。
素振りなどの基礎練習を疎かにしてシャトルを打つ練習を始めてしまうと、変な打ち方のクセがついてしまいます。これが原因で故障やケガをしてしまうケースもあるのです。
ただ素振りをすると言っても目標がないとやる気が出ないと思います。そこでおすすめしたいのは旗(タオル)打ち練習です。旗打ち練習は学校の体育館であれば2階の観覧席から、使い古したタオルやシーツなどを吊るしてラケットを使いオーバーヘッドストロークでそれを打つ練習方法です。
ラケットのストリングス面(ガットが張ってある部分)が真っ直ぐに当たれば甲高い良い音がします。真っ直ぐ当たらなければ、低い音しか出ません。腕力だけで目一杯タオルを打っても甲高い音は出ないのがこの練習の奥深いところです。
まずはこのタオル打ち練習で甲高い音の出るオーバーストロークができるようになることを目標としましょう。これができるようになっていればラケット面が真っ直ぐ出ているはずなので空振りが減るはずです。
参考:バドミントンの旗打ち練習!正しいフォームの作り方と打ち方
まとめ

空振りは、誰もが避けて通ることのできない失敗です。しかしそれを理由に「面白くない!できない!」と言ってバドミントンをやめてしまうのは非常にもったいないと思います。
正しい練習を積み重ねれば必ず上達していきます。最初からうまくプレーできる人はいません。素振り練習から始めて、成長していっているのです。
素振りやシャトル拾い、リフティングなどの練習が最終的には上達へつながっていきます。もし空振りをしても恥じることなく練習へ取り組みましょう。