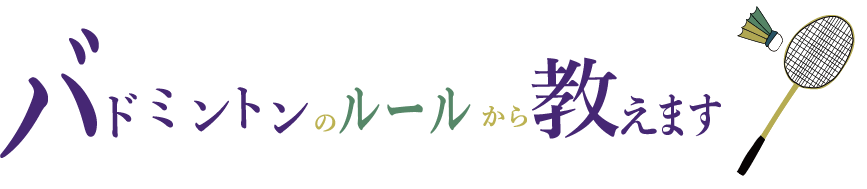バドミントンのルール上、ネット付近でフォルト(反則)となる場合はいくつか想定できる。
競技規則書を常に携帯して、内容を完璧に理解した上で主審として審判に臨むのが理想ですが、なかなかそうはできませんよね?
「今のってフォルト?それともレット?」と判断に迷うシチュエーションが、たまに出てきます。例えば俗にいうブロックショットなんて判定に迷いませんか?
今回は試合中にネット際でやってしまいがちなフォルトと、フォルトかレットか判断が難しい場合についてお話しします。
スポンサーリンク
バドミントンのルールでネット付近でフォルトとなるときって?

たとえばバレーボールのブロックのように、相手ショットの妨害を意図したブロックはバドミントンでは禁止されている。これにはブロックショットという俗称があり、競技規則書の第13条フォルト第4項(4)に該当します。
第13条フォルト
第4項インプレーで、プレーヤーが
(4) 相手を妨害したとき、すなわち、ネットを越えたシャトルを追う相手の正当なストロークを妨げたとき
引用元:競技規則(公益財団法人 日本バドミントン協会採択)
例えば、ヘアピンショットの応酬でラリー中にヘアピンが浮いたのをプッシュショットで打とうとしたら、相手プレーヤーがラケットでブロックをしてきた場合。これは明らかなフォルトになります。
ですが、相手プレーヤーにブロックするつもりがなく、相手が振ったラケットにシャトルが偶然当たって自分のコートへシャトルが入ってきた場合は、フォルトにならない可能性が出てくる。このケースは主審の判断によって決められます。
加えて言うならば、ネットの近くで打たれて自分の顔や身体を守るために出したラケットに偶然シャトルが当たって、相手コートへ入った場合もフォルトにならない。
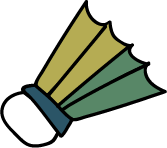
シャトルがネットにひっかかった場合はフォルトかレット(無効)か
自分が打ったシャトルがネットを越えたが、ネットにひっかかってしまった場合はフォルトでしょうか?それともレット(無効)になるでしょうか。競技規則書の第13条フォルト(2)に下記のようにあります。
第13条 フォルト
次の場合は「フォルト」である。バドミントン上達の秘訣を公開!!
◎桃田賢人選手を指導するコーチが監修!
◎プロの指導者がどのように教えてるか公開!
今やっている練習が実力につながっているか不安なら必見です!下記の画像を今スグにタップしましょう!!
>>>>>日本代表コーチが教える練習方法を知りたいならココをタップ!<<<<<
このアイテムについての口コミや評判を下記の記事にまとめてあります。ぜひチェックしてください!
【桃田賢斗選手の指導者】バドミントンシングルス勝つための必勝法と練習の極意【中西洋介コーチ監修】
この教材の最大の魅力は国内のトッププレーヤーと同じ練習メニューが分かること。またその練習の意義がしっかりと学べる点です。 普段の練習では言われた通り、もしくはいつもと同じ流れで同じ練習メニューをなんと ...
続きを見る
第2項 サービスでシャトルが
⑴ ネットの上に乗ったとき
⑵ ネットを越えた後、ネットにひっかかったとき
⑶ レシーバーのパートナーによって打たれたとき引用元:競技規則(公益財団法人 日本バドミントン協会採択)
つまり、サービスのときならネットにひっかかったり、ネットの上に乗ったらフォルト。
それでは、ラリー中にネットは越えたがネットに引っかかってしまった場合の判断はどうなるでしょうか。答えは、ラリー中となると第13条(2)という判定にはならず、第14条第2項(3)②が適用される。
第14条 レット
第1項 「レット」は、プレーを停止させるため、主審またはプレーヤー(主審がいないとき)によってコールされる。第2項 次の場合は「レット」である。
~中略~
⑶ サービスが打ち返されて、シャトルが
①ネットの上に乗ったとき
②ネットを越えた後、ネットにひっかかったとき引用元:競技規則(公益財団法人 日本バドミントン協会採択)
「フォルト」にするか「レット」とするか判断に迷うところですが、第14条第2項(3)②に該当し「レット」となります。「レット」となった場合は、その前のサービス以後のプレーは無効とし、レットになる直前のサーバーが再びサービスすることとなっている。
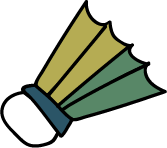
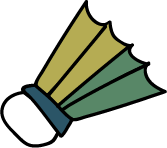
他にもフォルトとなるケースはサービス時が多いので、下記の記事にて詳しく記載しています。参考にしてみてください。
参考:バドミントンのルールでサーブフォルト(反則)になる場合は?
-



バドミントンのサーブに関するルール(規定)|反則にならないために気をつけるポイント!
バドミントンのルールでサーブフォルト(反則)となる可能性は、初心者に限らず中級者でもありえます。 正しいサーブ(サービス)の仕方を習得できていなければ、大会に出てもラリーを始めることなく ...
続きを見る
バドミントンのブロックはフォルト!


試合中は、想定できない事態がときどき発生します。その場合は落ち着いて競技規則書を確認すること。競技規則書を確認しても判断ができない場合は、競技役員長(レフェリー)へ相談しましょう。うやむやなまま試合を続行しては、その後の判定にプレーヤーも観客も疑いを持ちます。
上記の内容も競技規則書の第17条に規定されている。そのため競技規則書に定められていない事態が発生した場合のことについても言及してありますので、毅然とした態度で主審を務めましょう。
あなたがプレーヤーの立場だったら、自身のなさそうな審判に判定をされるのはイヤですよね?誰だって同じように思っているので、主審だけに判定を頼るのではなく、自分自身でもバドミントンのルールをしっかりと理解しておくことが大事。
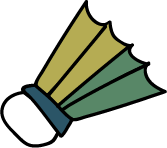
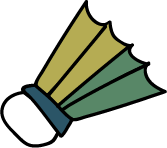
負けてばかりじゃ面白くないですよね?
もしも日本代表選手のコーチに教えてもらえたら、あなたも試合で勝てるようになると思いませんか。日本代表選手を指導するプロコーチからの教えですよ?
そのプロの指導方法が下記で公開されています。今すぐタップして内容をアナタ自身の目で確かめてください。いつ非公開になるか分かりません。
>>>>>日本代表コーチが教える必勝法を知りたいならココをタップ!<<<<< 

この教材の特徴や評判についてい知りたいなら、下記の記事をチェックしてみてください。
-



【桃田賢斗選手の指導者】バドミントンシングルス勝つための必勝法と練習の極意【中西洋介コーチ監修】
この教材の最大の魅力は国内のトッププレーヤーと同じ練習メニューが分かること。またその練習の意義がしっかりと学べる点です。 普段の練習では言われた通り、もしくはいつもと同じ流れで同じ練習メニューをなんと ...
続きを見る