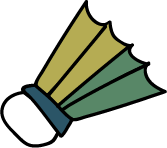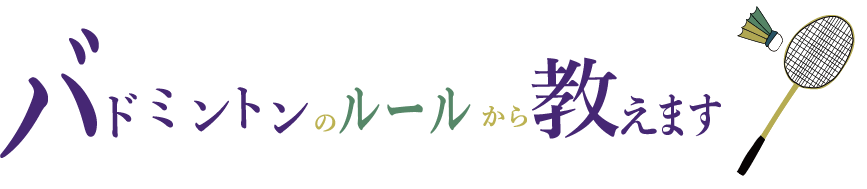バドミントンのルールでフォルトとなる場合については、競技規則書第13条に記載されています。しかし、これらのフォルトに内容ごとの正式名称はありません。またフォルトのコール(言い方)については付録5の審判用語に記載されています。
正式名称はないのですが、フォルトの内容ごとに一部「俗称」がついているのです。これはあくまで俗称であるため、公式試合で審判から正式に通達される言葉ではありません。
それでも練習中にフォルトの俗称が出てきたときに、内容が理解できないと困りますよね?このページでは競技規則書に書いてあるフォルトの内容で意味が複雑な項目と俗称がある項目について解説していきます。
競技規則の条文についてはこちらのリンクを参照してください。⇒公益財団法人 日本バドミントン協会 競技規則
目次
バドミントンのサービスフォルトの名称(俗称)
インプレー(ラリー中)以外でフォルトをしやすいのはサービス(サーブ)をするときです。正しいサービスについては、競技規則書の第9条第1項に記載されています。
まずはサービスをする側のフォルトの名称について解説していきます。
- フットフォルト・・・サーブを打つときに足が移動したり、上がったりしたとき。
- ライン・クロス・・・サーブを打つときにラインを踏んだり、越えたりしたとき。
- アバブ・ザ・ウエスト・・・サーブを打つとき、ウエストより高い位置で打ったとき。
- アバブ・ザ・ハンド・・・サーブを打つときラケットヘッドおよびシャフトが、シャトルを打つ瞬間に下向きでなかったとき。
この中でアバブ・ザ・ウエストとアバブ・ザ・ハンドは現行のルールになって変更されました。ルールの改訂前は手の位置よりラケット全体が下を向いてなければならないと定められていたので、その名残で現在もアバブ・ザウエスト、アバブ・ザ・ハンドと言う人がいます。
現在は競技規則第9条サービス第1項(6)で記載されているとおりコート面から1.15m以下でなければなりません。これに違反しているのをアバブ・ザウエストやアバブ・ザ・ハンドだと指摘する人がいる可能性があります。
名称はさておき1.15m以下の基準を守っていなければサービスフォルトに違いはないので、指摘を受け入れ改善していきましょう。
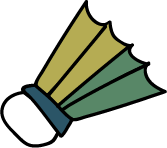
参考:バドミントンのルールでサーブフォルト(反則)になる場合は?
第3項(6)ヘルド・オン・ザ・ラケット(ホールディング)
まず規則内に専門用語で『ストローク』が出てきているので解説します。ストロークとは競技規則の定義で『プレーヤーのシャトルを打とうとするラケットの動き』と書いてあります。つまりラケットを振る行為です。
このことを理解した上で下記の第3項(6)を読み返すと疑問点が出てきませんか?
⑹ 1回のストロークで、ラケット上に捕えられ保持されて振り投げられたとき
引用元:競技規則(公益財団法人 日本バドミントン協会採択)
これはシャトルをラケットで保持してから打つ行為を禁止しています。
バドミントンをスポーツとして経験してないと、理解は難しいかもしれません。バドミントンはシャトル(羽根)を打ち合う競技という認識が一般的で、それが当然なのは言うまでもないです。
初心者のうちは難しいですが、ある程度の実力がついてくれば飛んできたシャトルをラケットで捕えて保持することができるようになります。それで一度ラケットで捕えたシャトルを相手へ打ち込むのを禁止しているのが、この規則=ヘルド・オン・ザ・ラケット(ホールディング)です。
あからさまにこのフォルトをするプレーヤーはいないでしょう。しかし、たまに怪しい打ち方をしているプレーヤーがいるのも事実です。そういうプレーヤーを練習中に見かけたら、このルールを教えてあげましょう。
第3項(7)の解釈
同じ選手が2回連続して打ってはいけないのは分かりますよね。そんなことが許されたら競技として成立しなくなってしまうでしょう。この反則をヒット・トゥワイス(ドリブル)と言います。
この第3項(7)でややこしいのは注釈です。
⑺ 同じプレーヤーによって2回連続して打たれたとき(ただし、ラケットヘッドとストリングド・エリアで、1回のストロークで連続して打たれるのは「フォルト」ではない。)
引用元:競技規則(公益財団法人 日本バドミントン協会採択)
これはラケットヘッドに当たって打ち返してしまってもフォルトとみなさないという意味です。ラケットヘッドに当たって打ち返したとしてもラリーに大きな影響はないと判断されているのでしょう。そのためラケットヘッドに当たって打ち返してしまったからといってラリーを中断する必要はありません。
2回連続で打ったと指摘されたらこのルールを相手と一緒に確認してみてください。
第3項(8)はダブル・タッチ
競技規則には第13条第3項(8)に『プレーヤーとそのパートナーによって連続して打たれたとき』と書いてあります。この条文から分かるようにこのルールは、ダブルスが対象となっています。
試合中にわざとパートナーが打つことはないでしょう。このフォルトが起きるのは、後衛のパートナーが下向きにシャトルを打ったとき前衛のラケットに当たってしまった場合などです。
他に想定されるケースは、前衛が打ち損なったシャトルを後衛が打ち返した場合でしょうか。この打ち損なったときに空振りではなくシャトルに触っていたら、たとえ後衛がリターンしてもフォルトになってしまいます。もし試合中に自分たちのペアがこのようなことになって、主審が気づいていないようなら自己申告してくださいね。
第4項(1)&(2) タッチ・ザ・ネット&オーバー・ザ・ネット

この第4項の(1)と(2)で定められているのはタッチ・ザ・ネットとオーバー・ザ・ネットについてです。下記に競技規則を引用しますので、まずは読んでみてください。
第4項 インプレーで、プレーヤーが
(1)ラケット、身体または着衣で、ネットまたはその支持物に触れたとき
(2)ラケットまたは身体で、ネットの上を越えて、少しでも相手のコートを侵したとき また、ラケットとシャトルとの最
初の接触点が、ネットより打者側でなかったとき(ただし、打者が、ネットを越えてきたシャトルを、1回のストロークで打つ場合、ラケットがシャトルを追ってネットを越えてしまうのはやむを得ない)引用元:競技規則(公益財団法人 日本バドミントン協会採択)
この第4項(1)のフォルトの俗称がタッチ・ザ・ネット。ネットの高さは競技規則の第1条で厳密に定められています。そのネットにむやみやたらに触ると、ネットが下がってしまう恐れがあります。そのためネットへ触れる行為を禁止しているのです。
またチェンジエンズの際などにネットをくぐるのは行儀が悪いと言われています。これもネットが下がってしまう可能性があるのでやめましょう。
インプレーでネットに触ることは規則書にフォルトと明文化してありますが、プレー中にネットへ触れることに関しては書いてありません。それでも前述したとおりマナー違反と考えている人が多いのでむやみやたらとネットへは触れなようにしましょう。
参考:バドミントンのルール・マナー、悪い態度は反則!?挨拶はしっかりと
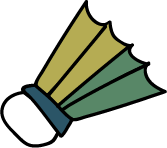
他にはダブルスでインプレー中に一方のプレーヤーがシャトルを追いかけているときに、パートナーがネットを触ってしまった場合でもフォルトになります。また規則内にもあるように支持物(ポスト)に接触してもフォルトとなりますので注意しましょう。
第4項(2)は、オーバー・ザ・ネットと呼ばれています。オーバー・ザ・ネットはプッシュショットを打った際に起こりやすいです。またプッシュは同時にタッチ・ザ・ネットも起こしやすいです。
この4項(2)はまず、自分のサイドからネットを越えて打ってはいけないとしています。注釈の部分はネットを越えてきたシャトルを打ったあとに、相手コートへラケットが侵入してしまうのは不問としています。
つまり、インパクト(シャトルを打った)後に、ラケットが相手のコートへ侵入するのは問題ありません。シャトルを打った後のラケットの動きをフォロースルーと言います。このフォロースルーによって相手コートへラケットが侵入するのはフォルトにならないとしているのです。
バドミントンのフォルトについてまとめ

フォルトにはさまざまな種類と名称があることをご理解いただけたと思います。いきなりすべてを覚えろと言われても難しいと思います。少しずつでいいので、何がフォルトになるのか覚えていきましょう。
このページで紹介した名称を覚えなくとも試合はできますし、主審を務めることも可能です。ただし一緒にバドミントンをプレーをする人が何を言っているのか分からないと困るので、フォルトの名称を覚えておくと便利でしょう。大事なのはフォルトを犯さないことです。
特にタッチ・ザ・ネットは初心者が犯しやすいフォルトなので、練習中からネットに触れる習慣をつけないようにするといいです。