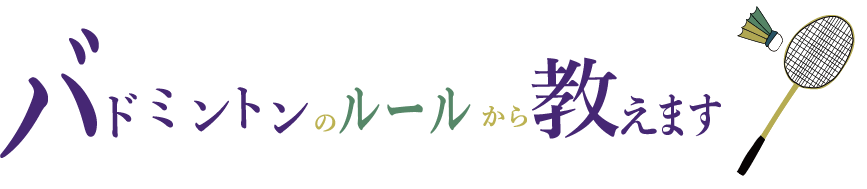バドミントンでは手首は固定して回内運動を使ったほうがよくシャトルは飛びます。しかし、この手首の使い方を間違えてしまうと、なかなかシャトルの飛距離は伸びません。
ラケット性能の向上により現在のバドミントンは一昔前と比較した場合、スピード化が著しいです。そしてこのスピード化は、これからもラケット性能の向上によってより進んでいくでしょう。
つまり、これからは男女子問わず可動範囲を小さくして、強く速いショットを打てるかが重要となってきます。そのためには、手首の使い方が大切です。今回はバドミントンにおける手首の使い方と重要性についてお話ししていきます。
バドミントンの手首の使い方と回内の運動
バドミントンの手首の使い方を説明する上で回内の運動について理解する必要があります。回内運動とは手首の動かし方というよりは、腕の筋肉の使い方。
回内運動を正しく感じるためには、腕を体の真横に伸ばして床と平行となるようにして肘を支点として腕を前後に動かしてみて下さい。これが回内運動で、この動きをそのまま頭上に持ってきて行うことによってシャトルに正しく力を伝えることができる。
この手首の使い方は初心者が陥る間違いのひとつで、この過ちに気付けないままバドミントンを続けると今後の上達に大きな影響を与えます。
バドミントンで誤った手首の使い方

画像のような招き猫の手は、手首を前に倒しています。これを掌屈(しょうくつ)といいます。初心者は間違ってバドミントンでこの掌屈運動をよくやってしまう傾向にあります。
この掌屈をすると、強い球や遠くに飛ばす球は打てません。シャトルを飛ばすにはスイングスピードが速いほうがいいのですが掌屈を使うとスイングスピードが遅くなってしまうのです。さらに手首を痛める確率が上がりますのでメリットは何もありません。
自覚のない本人は手首に力を入れているので、なんとなく飛ばせているような気がするのですが、飛ぶような気がしているだけで、実際には大きな力のロスをしてしまっているのです。
バドンミントンにおける正しい手首の使い方
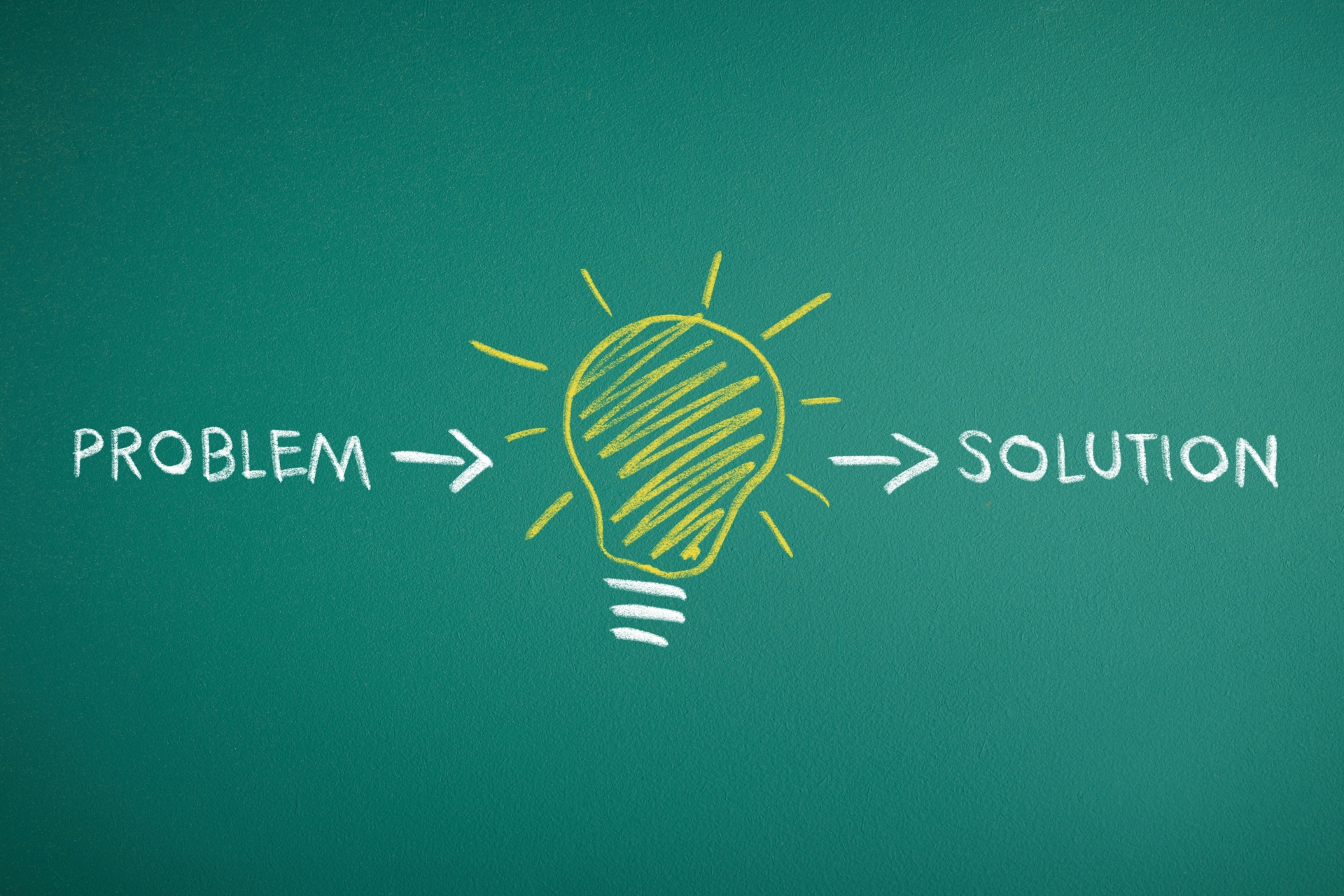
中級者以上の選手が手首で打っているように見えるのは、イースタングリップでラケットを持って回内運動と回外運動を使いこなせているからです。
回内運動は、前腕を手の平が下を向くように回転させることです。一方で回外運動は、前腕を手の平が上を向くように回します。実は無意識に日常生活の中で回内運動と回外運動を私たちは使っているのです。
日常生活の中でドアのノブを開けたり閉めたりするのを思い出してください。ドアノブを回すときの前腕の使い方が回内、回外です。
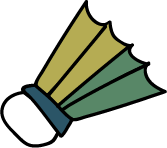
この動きを意識してラケットのスイングに応用するとシャトルが遠くまで飛ぶようになり、シャトルスピードのアップにつながる。
参考:バドミントンの旗打ち練習!正しいフォームの作り方と打ち方
手首は固定した方がシャトルは飛ぶ
バドミントンでは手首は使わずに、固定しましょう。そうすると体の回転(ひねり)、肩の回転、肘の力がロスせずにシャトルに力が伝わります。
オーバーヘッドストロークでもサイド(アーム)ストロークスでもスムーズに行うには、構えているときに腕とラケットを一直線にせず、手首を親指側に少し立てた状態にすることが重要です。この手首を少し立てた状態をリストスタンドと言います。
この際、手首とラケットとの角度が120度ぐらいになるようにします。練習中に指導者の方からよく「ラケットヘッドが下がっている」と言われる人は、このリストスタンドができていないということです。
参考:バドミントンでスマッシュレシーブが飛ばない原因は手首と肘にある
まとめ

バドミントンは手首の力と使い方が重要と表面的な意味だけで捉えて、間違った手首の使い方をしているといつまで経ってもシャトルが飛ぶようにはなりません。
正しい意味を理解して回内運動・回外運動が使えるようになればシャトルを遠くへ飛ばすことも可能となりますし、ショットスピードも向上する。
正しい打ち方を覚えてトレーニングをしていけば、バドミントンの実力の向上をハッキリと感じることができるでしょう。バドミントンの壁打ちを家でやる!自宅で使える壁打ち専用の板がある!?の中でお伝えしている練習もこの回内運動・回外運動を意識して練習してくださいね。